次元解析について確認しておきましょう.
高校で扱う単位はm(長さ),kg(質量),s(時間),A(電流)を基本単位としたMKSA単位系です.MKSA単位系にK(温度)やmol(物質量)などを基本単位として加えた単位系をSI(国際単位)といいます.
基本単位を組み合わせた単位を組み立て単位といいます.組み立て単位を構成する基本単位の数を次元(ディメンジョン)といいます.次元は長さを[L] ,質量を [M] ,時間を[T] ,電流を[I] として,$\rm [L]^k[M]^l[T]^m[I]^n$と表します.例えば,速さm/sの次元は$\rm [L][T]^{-1}$です.最近のセンター試験では次元を問う問題が出題されることが多かったので,自信のない人は練習しておきましょう.
解答欄の選択肢の中には次元の異なる解答もあります.例えば,分子運動論の立方体の箱に封入された分子が,1つの壁を単位時間に叩く回数を問う問題の選択肢として$\frac{v}{2L}$と$\frac{2L}{v}$があったとき,その2つの次元解析をすると,前者の単位は /sになるのに対して,後者の単位はsです.したがって,単位時間に壁を叩く回数として後者はふさわしくありません.問いによっては次元解析することで正解を導くことができる場合や,見直しをするときに次元解析をすることで間違いを見つけることもあります.上手く活用してください.
それでは共通テストまであと1日です.がんばってください.
#高校物理 #共通テスト #次元解析



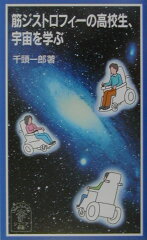
0 件のコメント:
コメントを投稿