寺田寅彦は明治から昭和にかけて活躍した物理学者。同時に,優れた随筆家としても知られており,その文才は夏目漱石に愛されたほどです。一見相反するような2つの才能を持ち合わせた寅彦について,本書の中で作家や俳人,研究者らがそれぞれの思いを語っています。
若き日の寅彦が行ったX線結晶解析は,物理学がマクロなものからミクロなものへ向かう当時において先進的なものでした。同研究でノーベル賞を受賞したブラッグ父子に遅れること数ヶ月。わずかな差で栄誉を逃しました。通信機器が十分に発達していなかったこと,日本での物理学の歴史が浅かったことを考えれば驚異的なことです。しかし,なぜかその後は金平糖や割れ目,墨流し,火花などを研究テーマとして物理学の本流から外れていきますが,それらのテーマはコンピュータが発達した現代において,非常に興味深いものです。寅彦の先見の明には驚かされます。寅彦の先見は随筆にも現れており,現代ではカオスやフラクタルで扱われる事象や,大陸移動説を示唆する内容まであります。本書の編集者である池内了氏は,寅彦の随筆を科学の宝庫と表しています。
寅彦は自然の神秘を化け物と表しています。「科学の目的は実に化け物を探し出すことなのである。この世がいかに多くの化け物によって充たされているか教えることである」 自然を愛していた寅彦は,化け物の存在から目を背けることができなかったのでしょう。身の回りのあらゆるところに潜む化け物を探し出しては,研究テーマとしたり,随筆に記したりしたのでしょう。さらに,絵画や音楽,映画にまで何らかの化け物を見たのではと感じます。
本書では,様々な分野の識者が,寅彦に潜む化け物をあぶり出そうとしているように感じます。私自身,寅彦の中にどんな化け物を見るのか楽しみです。買いためた寅彦の随筆集をじっくり読んでみよう。(寅彦と冬彦,池内了編集,岩波書店)
Translate
このブログを検索
C16
YouTube
-
目次 物理学とは 物理学とは何か?高校物理を学ぶための準備など 力学 運動の表し方や運動の法則,仕事と力学的エネルギー,運動量,剛体,力のモーメント,円運動,単振動,万有引力など 熱 熱量保存則,三態変化,気体の状態変化,気体がする仕事,熱機関,熱力学の法則,気体分子運動論な...
-
3.熱 目次 5.電磁気学 4.1. 波の基本的な性質 4.1.1.波とは 4.1.2.横波と縦波 4.1.3.空間での広がりを表す波の式 4.1.4.ある位置での振動を表す波の式 4.1.5.波の式 4.1.6.波の式と位相 4.1.7.波の式と波の伝搬方向 4.1...
-
4.波 目次 6.20世紀以降の物理学 5.1.電場と磁場の発見 5.1.1.電荷 5.1.2.電荷と原子の構造 5.1.3.静電気力 5.1.4.磁気力 5.1.5.電気と磁気の相互作用 5.1.6.電磁場の発見 5.1.7.電場と磁場 5.1.8.物質の電気的性質...




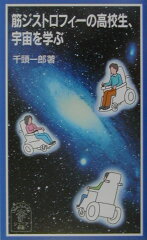
科学者の本質を見抜く力は素晴らしいものがあると感じています。その科学者の1人寺田寅彦をして,「化け物」と言わしめる自然の神秘。自然は偉大ですね。
返信削除